「うちの医院は大丈夫だろう…」
「スタッフ同士も仲が良いし、ハラスメントなんて無縁だ」
そう思っていても、職場の人間関係はデリケートなものです。何気ない一言や行動が、スタッフを深く傷つけ、ハラスメントトラブルに発展するケースは少なくありません。
特に、閉鎖的な空間になりがちな歯科医院では、一度人間関係にヒビが入ると修復が難しくなります。スタッフが安心して働ける職場環境を作るためには、ハラスメント対策が不可欠です。
今回は、歯科医院の院長先生が今すぐできるハラスメント対策を、マニュアル形式で分かりやすく解説します。
1. ハラスメントとは何かを正しく理解する
「ハラスメント」と一口に言っても、さまざまな種類があります。まずは、代表的なものを正しく理解しましょう。
パワーハラスメント(パワハラ): 優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること。
例: 他のスタッフの前で長時間にわたり叱責する、人格を否定するような発言をする、仕事を与えない、無視をするなど。
セクシュアルハラスメント(セクハラ): 職場における性的な言動によって、スタッフの意に反して不利益を与えたり、就業環境を害すること。
例: 性的な冗談を言う、プライベートな性的情報を尋ねる、体を触るなど。
マタニティハラスメント(マタハラ): 妊娠・出産、育児休業などを理由として、不利益な取り扱いをしたり、嫌がらせをしたりすること。
例: 「子育てが大変なら辞めたら?」と退職を促す、育休取得を認めないなど。
ポイント:
ハラスメントは、言われた側の受け取り方が重要です。「冗談だった」「悪意はなかった」は通用しません。
2. ハラスメント防止のためのルールを定める
ハラスメントを未然に防ぐためには、院内で明確なルールを設けることが最も効果的です。
ハラスメント防止方針の明確化:
就業規則に「ハラスメントの禁止」に関する規定を盛り込みましょう。
院長先生が率先して「ハラスメントは絶対に許さない」という強いメッセージを、朝礼やミーティングで発信することが重要です。
相談窓口の設置:
ハラスメントの被害に遭ったスタッフが、安心して相談できる窓口を設置しましょう。
内部のスタッフだけでなく、外部の専門家(社会保険労務士など)を窓口に設定することで、より相談しやすい環境を作ることができます。
ルールをスタッフ全員に周知する:
作成したルールや相談窓口の情報を、スタッフ全員に周知徹底しましょう。
新入スタッフが入社する際には、必ず説明する時間を設けてください。
ポイント:
ルールを作るだけでなく、そのルールがきちんと機能しているか、定期的に確認することが大切です。
3. 普段からできるハラスメント予防策
ルールを設けるだけでなく、日頃のコミュニケーションを工夫することで、ハラスメントの芽を摘むことができます。
「指導」と「叱責」を区別する:
スタッフを指導する際は、「なぜそれが問題なのか」「どうすれば改善できるのか」を具体的に伝えましょう。
感情的に怒鳴ったり、人格を否定するような言葉を使ったりするのは絶対にNGです。
叱る際は、人目につかない場所で個別に話すなど、配慮も重要です。
積極的なコミュニケーション:
日頃からスタッフ一人ひとりと向き合い、業務以外の雑談も交えながら、信頼関係を築きましょう。
「最近何か困っていることはない?」など、声をかけるだけでも、スタッフは安心できます。
定期的な研修の実施:
ハラスメント防止に関する研修を定期的に実施し、スタッフ全員の意識を高めましょう。
特に、院長先生自身が率先して受講することで、職場全体の意識が向上します。
まとめ:ハラスメント対策は「安心できる職場づくり」そのもの
ハラスメント対策は、院長先生の「スタッフに気持ちよく働いてほしい」という思いを形にするための重要なステップです。
ハラスメントのない、風通しの良い職場は、スタッフの離職率を下げ、チームワークを高め、結果として患者様へのより質の高いサービス提供に繋がります。
この記事を参考に、あなたの歯科医院のハラスメント対策を見直してみてはいかがでしょうか。

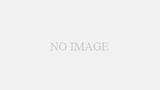
コメント