「まさか、うちの医院でこんな問題が起きるなんて…」
歯科医院の経営者として、労務トラブルは絶対に避けたいものです。しかし、給与の未払い、不当解雇、ハラスメントなど、ひとたびトラブルが発生すると、解決には多大な時間と費用、そして精神的なエネルギーを要します。
労務トラブルの多くは、日々の労務管理を適切に行うことで未然に防ぐことができます。今回は、実際に歯科医院で起こりやすい労務トラブルの事例を挙げながら、その予防策を解説します。
—
#### 事例1:残業代の未払いを巡るトラブル
**【事例】**
スタッフAさんは、診療後の片付けや翌日の準備のため、毎日15分〜30分ほど残業をしていました。しかし、タイムカードは定時で押すように指示されており、残業代は支払われていませんでした。退職後、Aさんは未払い残業代の支払いを求めて労働基準監督署に申告しました。
**【なぜ起こるのか】**
*労働時間の認識のズレ: 院長先生が「片付けは残業ではない」と考えていても、スタッフにとっては「業務」です。
*勤怠管理の不備: タイムカードを定時で打刻させるなど、正確な労働時間の記録を妨げる行為は、後々のトラブルに直結します。
**【予防策】**
*1分単位での正確な勤怠記録: 勤怠管理システムを導入し、出勤から退勤まで1分単位で正確に記録しましょう。
*残業代のルールを明確に: 就業規則に「所定労働時間を超えて労働した場合は、1分単位で残業代を支払う」と明記し、スタッフ全員に周知しましょう。
*業務の効率化: 終業後の片付けや準備にかかる時間を短縮できるよう、業務フローを見直しましょう。
—
#### 事例2:ハラスメントを巡るトラブル
**【事例】**
院長先生は、診療中のミスが多い歯科助手Bさんに対し、他のスタッフの前で「こんなこともできないのか!」と感情的に叱責することが度々ありました。Bさんは精神的に追い詰められ、退職。その後、不当な叱責は「パワハラ」にあたるとして、損害賠償を求めました。
**【なぜ起こるのか】**
*指導と叱責の区別がついていない: 業務上の指導と、人格を否定するような叱責の境界線が曖昧になっている。
*ハラスメント対策の不備: ハラスメントに対する院の方針や相談窓口が明確になっていないため、問題が表面化しにくい。
**【予防策】**
*ハラスメント防止の研修: 院長先生自身がハラスメントに対する正しい知識を身につけ、スタッフ全員にも定期的な研修を実施しましょう。
*指導方法の見直し: 感情的に叱るのではなく、「なぜその行動が問題なのか」「どうすれば改善できるのか」を具体的に、**人目のつかない場所**で伝えましょう。
*相談窓口の設置: ハラスメントの被害に遭ったスタッフが安心して相談できる窓口を、就業規則に明記しましょう。
—
#### 事例3:有給休暇取得を巡るトラブル
**【事例】**
スタッフCさんが有給休暇を申請したところ、「忙しいから他の日にしてくれないか」と院長先生から断られてしまいました。Cさんは何度も申請しましたが、その都度断られ、結局有給休暇を消化できずに退職することになりました。
**【なぜ起こるのか】**
*有給休暇に対する誤った認識: 院長先生が有給休暇を「医院の都合で与えるもの」と捉えている。
*シフト管理の不備: スタッフが休んだ場合の代役を確保できないため、院長先生が時季変更権を安易に行使してしまう。
**【予防策】**
*有給休暇はスタッフの権利と認識する: 法律で定められたスタッフの権利であることを理解し、原則として希望通りに取得させましょう。
*有給休暇管理簿を作成する: スタッフごとの有給休暇の付与日数、取得日数、残日数を正確に管理しましょう。
*有給休暇の計画的付与: 有給休暇の取得希望日を事前にヒアリングし、シフト調整を工夫しましょう。
—
#### まとめ:労務トラブルの予防は「安心」への投資
労務トラブルは、ひとたび発生すると医院の評判や経営に大きなダメージを与えます。
*残業代: 正しい勤怠管理と給与計算で未払いを防ぐ。
*ハラスメント: 正しい知識を身につけ、ハラスメントのない職場を作る。
*有給休暇: 法律を遵守し、スタッフの権利を尊重する。
これらの予防策は、単なる「守り」ではなく、スタッフに「この医院は安心して働ける」というメッセージを伝える**「未来への投資」**です。もし、これらの予防策に不安がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談し、一度チェックしてもらうことをお勧めします。

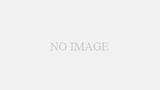
コメント