「うちのスタッフが妊娠したって言ってきたけど、どう対応すればいいんだろう…」
「産休・育休の制度は知っているけど、小さな医院でも運用できるのかな…」
歯科医院にとって、スタッフの妊娠や出産は喜ばしいニュースである反面、院長先生にとっては「どうやって業務を回していこうか…」という不安も同時に生じるかもしれません。
しかし、産休・育休制度は法律で定められたスタッフの権利であり、正しく理解して運用することは、優秀な人材の定着に不可欠です。働きやすい制度を整えることは、スタッフのモチベーションを高め、結果として医院の成長にも繋がります。
今回は、歯科医院で働くスタッフが安心して妊娠・出産を迎えられるよう、知っておくべき制度の基本と、具体的な制度の作り方をご紹介します。
産前産後休業と育児休業の違いを理解する
まず、スタッフが取得できる休業には、「産前産後休業」と「育児休業」の2種類があります。
産前産後休業
対象:雇用形態に関わらず、妊娠中のスタッフ全員が対象です。
期間:
産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から。
産後休業:出産の翌日から8週間。
ポイント:産後8週間は法律で就業が禁止されており、スタッフ本人が働きたいと申し出ても働かせることはできません。
育児休業
対象:原則として、1歳未満の子どもを養育するスタッフが対象です。条件を満たせば、パートやアルバイトスタッフも取得できます。
期間:子どもが1歳になるまで(特別な事情がある場合は最長2歳まで延長可能)。
ポイント:育児休業は、男女ともに取得できる権利です。最近では男性スタッフの育児休業取得も増えてきています。
育児休業中の給与はどうなる?
スタッフが休業中の給与について不安に感じることは多いでしょう。
給与:産前産後休業中、育児休業中は、原則として給与の支払い義務はありません。
手当:その代わり、健康保険から「出産手当金」(産前産後休業中)や、雇用保険から「育児休業給付金」(育児休業中)が支給されます。
ポイント:これらの手当はスタッフが直接申請する手続きですが、医院側が手続きをサポートすることで、スタッフは安心して休業に入ることができます。
小さな歯科医院でもできる働きやすい制度の作り方
法律で定められた制度を守るだけでなく、さらに一歩進んだ働きやすい環境を整えることで、スタッフは「この医院で長く働きたい」と感じてくれます。
育児短時間勤務制度の導入:3歳未満の子どもを養育するスタッフが、短時間勤務を希望した場合、原則としてこれを認めなければなりません。
たとえば、「9時から16時までの勤務」や「週4日勤務」など、柔軟な働き方を導入することで、子育てと仕事の両立を支援できます。
職場復帰に向けた支援:休業中のスタッフと定期的に連絡を取り、職場復帰への不安を軽減しましょう。
復帰する際には、ブランクを埋めるための簡単な研修や、新しい機器の操作説明などを行うことで、スムーズに仕事に戻れるようにサポートしましょう。
「助け合いの文化」を醸成する:スタッフ全員で、「誰かが休んだ時は、みんなで助け合う」という意識を共有することが何よりも大切です。
日頃から業務のマニュアル化を進めておけば、急な欠員が出た場合でも、他のスタッフがスムーズにカバーできます。
まとめ:制度の整備は「未来への投資」
産休・育休制度への対応は、単なる法的な義務ではありません。それは、スタッフを大切にし、長く働いてもらいたいという院長先生の想いを形にする「未来への投資」です。
働きやすい環境が整った歯科医院は、スタッフの満足度を高め、離職率を下げ、結果として患者様からも選ばれる医院へと成長します。
まずは、法律で定められた制度を正しく理解し、スタッフに「いつでも相談してね」と声をかけることから始めてみませんか。

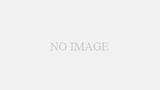
コメント