「労働法規って、難しそうでよくわからない…」
「うちの医院は大丈夫だと思っているけど、何から勉強すればいいんだろう?」
歯科医院を経営する上で、労働法規の遵守は不可欠です。しかし、法律の条文は専門的で理解しにくく、日々の診療に追われる院長先生にとっては、なかなか勉強する時間が取れないかもしれません。
労働法規を軽視すると、未払い残業代や不当解雇といった労務トラブルに発展し、医院の評判や経営に大きなダメージを与えてしまいます。今回は、歯科医院の院長先生がこれだけは知っておくべき、労働法規の基礎知識を3つのポイントに絞って解説します。
労働時間と残業代:1分単位の記録と支払いが必須
労働時間と残業代に関するトラブルは、労務問題の中でも特に多く発生します。法律の基本をしっかりと理解しておきましょう。
労働時間の定義:労働基準法では、スタッフが院長先生の指揮命令下に置かれている時間を「労働時間」と定めています。例えば、朝礼、終業後の片付け、研修、着替えの時間なども、原則として労働時間に含まれます。
残業代の計算方法:
法定労働時間:原則として「1日8時間、週40時間」です。
時間外労働:法定労働時間を超えて働いた場合、割増賃金(1.25倍以上)を支払う義務があります。
深夜労働:午後10時〜午前5時に働いた場合、割増賃金(1.25倍以上)を支払う義務があります。
休日労働:法定休日(週1回または4週間に4回)に働いた場合、割増賃金(1.35倍以上)を支払う義務があります。
ポイント:労働時間は1分単位で正確に記録し、残業代は働いた分を全額支払いましょう。サービス残業は法律違反です。
雇用と解雇:法律に則った手続きが重要
スタッフを雇用する際、そして残念ながら解雇する際には、法律に則った手続きが必要です。安易な判断は、後々大きなトラブルに発展します。
雇用契約書の作成:従業員を雇用する際は、雇用形態にかかわらず、給与、労働時間、休日などを書面で明記した「労働条件通知書」を交付する義務があります。
解雇のルール:労働基準法では、解雇は客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にのみ許されます。
解雇予告:解雇する際には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の**解雇予告手当**を支払う必要があります。
「普通解雇」と「懲戒解雇」:無断欠勤が続く、能力不足などによる「普通解雇」、重大な非違行為による「懲戒解雇」など、解雇の種類によって手続きや条件が異なります。
ポイント:解雇は非常にデリケートな問題です。自己判断で進めるのではなく、専門家である社会保険労務士に相談し、慎重に対応しましょう。
有給休暇:スタッフの「権利」として適切に付与・管理する
有給休暇は、スタッフの心身のリフレッシュを目的とした、法律で定められた権利です。
付与の義務:雇用から6ヶ月が経過し、全労働日の8割以上出勤したスタッフには、有給休暇を付与する義務があります。
年5日の取得義務:2019年からは、年10日以上の有給休暇が付与されるスタッフに対し、年5日を確実に取得させる義務が、院長先生に課せられています。
時季変更権:スタッフが希望した日に有給休暇を取得されると、業務の正常な運営を妨げる場合、院長先生は別の日に変更させることができます。しかし、これは「やむを得ない事情」がある場合に限られます。
ポイント:有給休暇は「医院の都合で与えるもの」ではありません。スタッフの権利として尊重し、適切に管理しましょう。
まとめ:労働法規の遵守は「安心」への投資
労働法規の基礎知識を身につけ、日々の労務管理を適切に行うことは、法的なリスクを回避するだけでなく、スタッフからの信頼を得る上でも非常に重要です。
労働時間と残業代:正しい記録と支払いを徹底する。
雇用と解雇:法律に則った手続きを怠らない。
有給休暇:スタッフの権利として尊重する。
これらのポイントを押さえることで、あなたの歯科医院は、スタッフが安心して長く働ける、信頼される職場になるでしょう。労働法規について不安がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

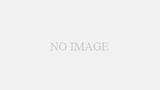
コメント